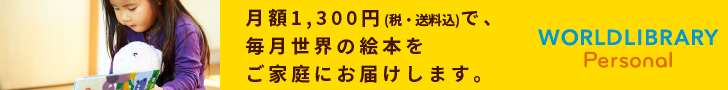はじめに
こんにちは、ワタナベです!
2025年4月末、我が家に待望の第二子、次女が誕生しました。 家族が増えた喜びと同時に、あの懐かしくも過酷な“夜泣きシーズン”が再スタート。
現在の我が家は、まさに“夜勤育児”の真っ只中。 毎晩10時から朝5時まで、ソファに座って抱っこしたまま、赤ちゃんの寝息を待ち続ける生活です。
この記事では、新生児期に見られる夜泣きの原因と、筆者が実際に試して「これは効いた!」と感じた5つの対策をご紹介します。
新生児の夜泣き、主な原因は“体の発達過程”にあり
新生児(生後0〜3ヶ月頃)の夜泣きは、決して“わがまま”ではありません。
彼らにとって泣くことは唯一の意思表示手段。
その背景にはさまざまな生理的要因があります。
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 空腹 | 胃がまだ小さく、満腹状態が長続きしないため、2〜3時間おきの授乳が必要です。 |
| オムツの不快感 | オムツが濡れていたり、蒸れていたりすると、不快で泣き出します。 |
| モロー反射 | 手足が急にビクッと動いて目が覚めることで、泣くことがあります。 |
| 浅い睡眠 | 新生児はレム睡眠の割合が高く、外部の刺激で起きやすい状態です。 |
| 環境の違和感 | 光、音、室温など、胎内とは異なる外の世界に順応できず、不安や不快を感じます。 |
こうした原因を理解しておくことで、夜泣きに対して冷静に対応できるようになります。
我が家で実際に効果を感じた夜泣き対策5つ
① おくるみで“安心感”を与える
モロー反射で何度も目を覚ます娘を見て、「これはスワドル(おくるみ)しかない!」と導入。
我が家が使ったのは、ファスナーで簡単に着脱できるスワドルアップ。 寝かしつけがぐんと楽になり、親の負担も軽減されました。
② 胎内音・ホワイトノイズを活用
赤ちゃんは、ママのお腹の中にいた時のような音に安心感を覚えるそうです。
無料アプリやYouTubeなどで胎内音ホワイトノイズを流すだけで、泣き止んだり、再び眠ってくれることがよくあります。
③ 授乳後のゲップは“必須ケア”
長女の時は手抜きしていたゲップケア。次女では丁寧に行うようにしました。
- 肩に担いで背中を軽くトントン
- 座らせて背中をさする
このちょっとしたケアだけで、授乳後すぐ泣くことが減り、スムーズに眠ってくれるようになりました。
④ オムツ替え+肌ケアの見直し
オムツ交換のたびに「赤ちゃんが泣く」「おしりが赤くなる」…そんな悩みが続いた時期も。
今では、刺激が少ないコットン+ぬるま湯で拭き取り、無添加のワセリンで保湿する方法に変更。
結果、おしりのトラブルが激減し、夜中に泣く頻度も下がりました。
▶︎ おむつかぶれがひどいときの対処法|実際に効いた市販薬&予防グッズまとめ
⑤ 室内の環境を整える
「寝てくれない」原因のひとつが、意外と“空気”や“光”だったりします。
我が家では以下を徹底:
- 室温:22〜24℃
- 湿度:50〜60%
- 間接照明を使用(暗めの環境づくり)
これにより、目覚めにくくなり、ぐっすり眠る時間が少しずつ増えてきました。
実際に使ってよかった夜泣き対策グッズ
| アイテム | 特徴 | 評価 |
| スワドルアップ | 着脱しやすく、モロー反射対策に最適 | ★★★★★ |
| ホワイトノイズアプリ | 無料で使いやすく、効果も抜群 | ★★★★☆ |
| 無添加ワセリン | 保湿力が高く、おしりかぶれ予防に◎ | ★★★★★ |
| デジタル温湿度計 | シンプルで見やすく、育児の必須アイテム | ★★★★★ |
夜泣きの“夜勤育児”、いつまで続く?
筆者は現在、毎晩の“夜勤”を担当中。
ですが、長女の時の経験からも、3ヶ月頃から夜まとまって寝てくれるようになった記憶があります。
生後3週間ほどですが、夜は4〜5時間はまとまって寝てくれるようになってきた気がします…
「今が一番つらい時期」と自分に言い聞かせつつ、便利なアイテムやパートナーとの協力で乗り越えていくことが大切です。
夜泣き対策には“頼れるサブスク”も有効
📚 WORLDLIBRARY Personal(絵本の定期便)
- 月齢に合わせた絵本が届く
- 読み聞かせルーティンがつくれる
- 親も選書のストレスから解放!
寝かしつけ前に絵本を読む時間を作ることで、赤ちゃんの“おやすみモード”が整い、スムーズな入眠に繋がりました。